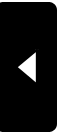2008年10月14日
2008年10月08日
盗まれました
うちの裏道は「泥棒ストリート」と呼ばれている。
畑の野菜とか、庭の花を盗まれまくってるのだよ。
まったくどこの不心得モノが!
出来心ではない証拠に、ヤツらは大量に、掘りとってまで盗んでいく。
ほうれん草は鎌で刈り取り、大根は引っこ抜き、ブロッコリーはナイフで切り取り…
これどう思う?犯人像がつかめん。
花にいたってはシャベル持参で豪快に掘りとっていく。
許さん。
さっき大株がなくなってるのを発見して地面に頭がめりこみそうになったよ…どーゆーつもりだ!泥棒だぞ!!
畑の野菜とか、庭の花を盗まれまくってるのだよ。
まったくどこの不心得モノが!
出来心ではない証拠に、ヤツらは大量に、掘りとってまで盗んでいく。
ほうれん草は鎌で刈り取り、大根は引っこ抜き、ブロッコリーはナイフで切り取り…
これどう思う?犯人像がつかめん。
花にいたってはシャベル持参で豪快に掘りとっていく。
許さん。
さっき大株がなくなってるのを発見して地面に頭がめりこみそうになったよ…どーゆーつもりだ!泥棒だぞ!!
2008年10月04日
ウィキペディアで調べてみた、近江弁
相手への軽い敬意と親しみを表す助動詞
近江弁では、代表的な近畿方言の敬語「はる」(「なさる」の転訛)を京都と同様に多くの場面で用いるほか、「はる」よりもさらに軽い敬意と親しみを表わす助動詞がある。
a音+ある、e音/i音+や(あ)る
「はる」とその古い形「やはる」がそれぞれ訛ったもの。湖東・湖北・湖南地域で用いるが、湖南地域ではややフラットな発音になる。
(例)しゃある(←しやはる) ぃやある(←居やはる) ゆわある(←言わはる) きゃある(←来やはる) 食べやある(←食べやはる)
連用形+やる
主に彦根周辺の女性が用いる。「や(あ)る」と同形になることがあるもののアクセントによる区別があり、例えば「食べやった」の「べ」にアクセントを付けると「やる」、「や」に付けると「やある」の過去形ということになる。
連用形+ら(あ)る
湖南・甲賀地域の一部などで用いる。
(例)言うてらる
連用形+やんす/んす
終助詞「ほん」
語尾につけて「だよ」「だぞ」「きっと…だよ」といったニュアンスを与える。湖東・湖北地域の広い範囲で用いる。一部で意思や勧誘の意味でも用いることがある。
(例)どうなっても知らんほん!(どうなっても知らないぞ!) 明日は晴れるほん。(明日はきっと晴れるよ) ほな行ってこほん。(じゃあ行ってくるよ)
原因・理由の接続助詞「さかい」「で」「し」
共通語での「ので」「から」に当たり、「さかい」の後ろには「に」をつけることがある。もとは滋賀県に限らず近畿地方で広く用いてきた表現だが、共通語「から」に押され京阪神では廃れており、滋賀県でも若年層では「から」が優勢になりつつある。湖北・湖西などでは「さけ」となることもある。「で」は湖北・湖東地域を中心に、「し」は湖西・湖南地域を中心に用いる簡潔な表現。
(例)もう年やさかい(に)/やで/やし、無理やわ。(もう年だから、無理だよ)
否定の助動詞「ん」「へん/ひん」「やせん/せん」「なんだ/へなんだ」「んかった/へんかった」
近畿方言では「ぬ」が撥音化した「ん」や「へん/ひん」を否定文に使用する(例:あかん、せえへん、しいひん)。この「へん/ひん」は、「はせぬ」の変形である「やせん/せん」がさらに変化して成立したものである。近江弁でも同様に「ん」「へん/ひん」を用いるが、年配者の間では今でも「やせん/せん」を用い、また「や(あ)る」の否定形に「やあれん」を用いることもある。否定の過去形には、共通語「なかった」が変化した新方言「んかった/へんかった」と、やや廃れつつある旧来の「なんだ/へなんだ」という一般的な近畿方言と変わらないものを用いる。
強調の副助詞「くらい」
湖東・湖北地域で用いる表現で、「くらい」の前につく動詞などを強調する。
(例)するくらい!(するさ/よ!)
命令・禁止の副助詞「さ」
湖東・湖北地域で用いる表現で、近畿方言で一般的な「な」「や」と併用される。
(例)はよしいさ(早くしなよ。一般的な近畿方言では「はよしいな」「はよしいや」)
終助詞「よ」
京阪神ではあまり用いないが、滋賀県では男女問わず多用する。後述「で」とついて「じょ」となることもある。
(例)ほやでよー(だからさぁ) …やけどよー(…だけどさぁ)
音便
他の近畿方言と同様に近江弁でもウ音便が盛んである。また湖東地域では「し」がイ音便化することがあり、その際イ音便後のタ行音がサ行音に変化することがある。
(ウ音便の例)暑くて→あつうて よく笑った→ようわろた
(イ音便の例)傘をさした→傘をさいた/さいさ 腰を抜かしてしまって→腰を抜かいでしもて/抜かいせしもて
s音のh音への転訛
これも近畿方言全般で多く見られることだが(例:すみません→すんまへん)、近江弁は京都・大阪以上にh音への転訛が盛んであり、京都・大阪の出身者からは田舎くさい印象を持たれることがある。
(例)はかい/はけ(上記の「さかい」「さけ」) ほーけー(そうかぁ) ほーよー(そうだよ) ほして/ほて(そして) ほしたら/ほたら(そしたら) ほな(それなら/それでは) ほれで/ほんで(それで) ほやほや(そうだそうだ) ほの(その) ほこ(そこ)
あおぢ
【名】あおたん。内出血。
あこかい
よく知られた近畿方言「あかん」をやんわり強めた派生表現。「あっかい」と促音化することもある。「あこかいや」「あこかいな」などとも。なお「あるかい(=あるわけなかろう)」の促音形「あっかい」という同音異義語もあるので注意。 (例)ほんなことしたらあっかいや。(そんなことしたら駄目じゃないか)
あっちべら
【名】あちら。:水口及びその近隣の地域で主に使われている。「向こうべら」と言う場合もある。なお、「こちら」は「こっちべら」である。
あんない
【形】「味がない」の転訛で、「美味しくない」という意味。
いかい
【形】大きい。古語の「いかし」に由来。 (例)しばらく見ん間(ま)にいこぉなってぇ。(しばらく見ないうちに大きくなって)
いぬ
【動】帰る。古語由来で、漢字では「去ぬ」「往ぬ」と表記する。かつては全県で使われてきたが、共通語の「帰る」におされて使用が減ってきている。
いの
帰ろ。
いんでこほん
「帰って行こう」の意味で、別れるときに使うことがある。
うい
【形】「憂鬱だ」という意味で、古語の「憂し」が由来。アクセントは低・高。「(相手に対して)申し訳ない」というような意味でも使われることがある。 (例)あー、ういなぁ。(あー、憂鬱だなぁ) ほんなことしてもろて、ういこっちゃ。(そんなことをしてもらって悪いことだ)
うたて
【形】鬱陶しい。古語「うたてし」の転訛。
うみ
【名】「海」という意味のほかに、「琵琶湖」という意味でも使われることがある。
えらい
【形】「偉い」のほかに、「とても」「しんどい」「とんでもない」という意味でも使われる。 (例)えらい仕事させられたさかいえらかったわ。(とんでもない仕事をさせられたから疲れたよ)
おおさらしい
【形】大袈裟だ。仰々しい。
おが
【名】カメムシ。
お…やす、…やす
【助動】お…なさい。…ください。 (例)おきばりやす(頑張ってください) お帰りやす(お帰りなさい) ごめんやす(ごめんください) あがっとくれやす(おあがりください) おいでやす(おいでください)
おっさん
【名】お坊さん。「お」にアクセント。フラットに発音すると、共通語の「おっさん」と同じ意味になる。
おまはん
「おまえさん」の転訛である「おまえはん」が縮まったもので、さらに縮めて「おまん」ということもある。「あんた」や「おまえ」よりも丁寧な印象を与えるが、若年層では使われなくなってきている。
かなん
「かなわぬ」の転訛で、「嫌だ」「やりきれない」という意味。京都や大阪でも通じる。
かばた
【名】水路に設けられた作業場のことで、漢字で書くと「川端」。「川端」は湖西地方で使われ、湖東地方では「かわと」(川戸)と呼ばれる。NHK特集で高島市新旭町針江地区の川端が紹介され、注目を集めた。
参考リンク:高島市新旭町針江地区ホームページ内「川端のご案内」
きずつない
【形】古語の「ずちなし」(=どうしようもない。困り果てたことだ)に「気」を合わせたもので、「どうしようもない状態に置かれて、(恥ずかしさなどで)その状態でいるのが申し訳なく感じられ、耐えるのがつらくて気が滅入っている様子」というような意味。 (例)人前でヘマをしてもて、気ずつなかったわ。(人前でヘマをしてしまって、どうしようもなく恥ずかしかったよ)
ごえんさん
【名】ご住職さん。「御院様」の変形。
こぼつ
【動】壊す。古語由来で、漢字では「毀つ」と表記する。
ごもく
【名】ゴミ。
じしん
【名】地震。「じ」にアクセントがくる。
…したらわ?
「…したらどう?」という意味の女性表現。
じん
【名】「人」をあえて音読みで読んだもので、対象の人物に対する相当な侮蔑が込められている。 (例)あのじん、ホンマうっさいわ。(あいつ、ホントうっせぇよ。)
…しとみない
「…するのは気が引ける」「~するのはなんとなく嫌だ」という意味。「…しとむない」とも。 (例)行きとみないなあ。(なんとなく行くの嫌だなあ)
知らんてる
知らないでいる。 (例)知らんてる間(ま)に大きいなって。(知らないうちに大きくなって)
すいばり
【名】ヤスリのかかっていない材木の角などにある木のトゲ。
せんどする
「くたびれる」の意で、「えらい」「しんどい」よりも強いニュアンス。「まるで仕事を千度(千回)するように感じるほど疲れる」ということから。湖北地方などで使われる派生語に「おせんどさん」(=お疲れさん)がある。 (例)あー、せんどした。(あー、くたびれた)
たいや
【名】法要の事。頭に「お」をつけて「おたいや」と使う場合もある。
だんない
【形】差し支えない。大丈夫だ。同義語に「構いはせぬ」の変形である「かまへん」がある。これは京都と同じ表現であり、大阪では「かめへん」となる。
ちゅんちゅん
お湯などが沸いている様子を表す擬態語。
ちょかちょか
あちこちをせわしなくうろちょろしている様子を表す擬態語。「する」をつけると「あちこち動き回っていて落ち着きがない」「あちこち動き回っていたずらをする」という意味になる。名詞化すると「おちょか」または「ちょか」。「ちょかる」(調子に乗る)や、それを名詞化した「ちょかり」(調子乗り)という派生表現もある。 (例)おちょかせんとき!(うろちょろしないの!/いたずらしないの!) ちょかってんなや!(調子乗ってるなよ!)
つうりんぼ
【名】干し柿。
どうで
どうして。なぜ。湖東地方で使われる。 (例)どうでそうなるん。(なんでそうなるの)
とこ
【名】家。家庭。 (例)うち(ん)とこは。(私の家では)
とさいが
…とだな。強調語。 (例)ほうするとさいが。(そうするとだな) こう暑いとさいが、やる気出えへん。(こう暑いとだ、やる気が出ない)
どんつき
【名】突き当たり。
なまずけない
【形】怠けている。不精だ。だらしがない。 (例)部屋ちっとも片付けんと!なまずけないやっちゃなあ!(部屋をちっとも片付けないで!だらしないやつだなあ!)
…ね
…んち。「…のいえ」が縮まったもの。 (例)うちね遊びに来ぃな。(私んちに遊びに来なよ) 田中さんねは立派な家やなぁ。(田中さんちは立派な家だなぁ)
はしかい
【形】古語の「はしかし」が転訛したもので、(細かいトゲなどが当たって)ちくちくと痛いという意味。派生して、風邪などでのどの奥がひりひりして気持ち悪いという意味もある。麻疹とは関係ない。
びちがく
【動】指先でつねる。
ぶんど
【名】湖北地方の年配者によく使われる、えんどう等の豆のこと。
ほっこりする
【動】疲れる。手を焼いた。疲れがとれてほっとする。
地域によってまったく正反対の意味になる。湖北地方などでは「おせんどさん」と合わせて「ほっこりおせんどさん」(=おつかれさん)となることもある。
…まい
【助動】…しよう。湖北地方などで使われる。 (例)いのまい。(帰ろう)
むっかい
【形】ムズい。「むつかしい」が略されてできた滋賀の若者言葉。
めいぼ
【名】目のイボ、つまり「麦粒種」のこと。東京の「ものもらい」や大阪の「めばちこ」という言い回しに比べて直接的でわかりやすい表現である。
めめんかす
【形】ほんの少しである様子。
ももける
【形】セーター等に毛玉が出来たことを表す。
もりこす
【動】湯水が容器の容量を超えて溢れて出てしまうこと。「漏れる」と「超える」が合わさったものか。 (例)うわ、お風呂のお湯もりこしたーるで!(うわ、お風呂のお湯が溢れ出してるよ!)
もんる
【動】帰る。寄る。「戻る」の転訛か。「もんる」単独ではあまり使われず、「もんてくる」(「もんる」+「くる」=帰ってくる)という表現で多く使われる。なお、彦根市のおいでやす商店街には「もんてくる」をモチーフにした「モンテ」(=寄っておいで)という名の施設がある。
もんろまい
「帰ろう」の意味で、別れるときに使うことがある。「いんでこほん」との明確な使い分けはない。
ようあんたさん
「どういたしまして」に近いニュアンスの表現。主に「おおきに」「おきばりやす」と声をかけられた時の返し言葉として使われる。
よぞくろしい、よぞい
嫌だ。不快だ。湖北で使われる。(「おぞ」ましく「狂おしい」か。)
よばれる
【動】(食事などを)頂く。「御馳走になる」以外にも広く用いる。 (例)こんなんしかあらへんけど、なんなっとよばれて。(こんなのしかないけど、なんなりと食べて)
抜粋してきたけど、こっそり読んでくださいよ。
近江弁では、代表的な近畿方言の敬語「はる」(「なさる」の転訛)を京都と同様に多くの場面で用いるほか、「はる」よりもさらに軽い敬意と親しみを表わす助動詞がある。
a音+ある、e音/i音+や(あ)る
「はる」とその古い形「やはる」がそれぞれ訛ったもの。湖東・湖北・湖南地域で用いるが、湖南地域ではややフラットな発音になる。
(例)しゃある(←しやはる) ぃやある(←居やはる) ゆわある(←言わはる) きゃある(←来やはる) 食べやある(←食べやはる)
連用形+やる
主に彦根周辺の女性が用いる。「や(あ)る」と同形になることがあるもののアクセントによる区別があり、例えば「食べやった」の「べ」にアクセントを付けると「やる」、「や」に付けると「やある」の過去形ということになる。
連用形+ら(あ)る
湖南・甲賀地域の一部などで用いる。
(例)言うてらる
連用形+やんす/んす
終助詞「ほん」
語尾につけて「だよ」「だぞ」「きっと…だよ」といったニュアンスを与える。湖東・湖北地域の広い範囲で用いる。一部で意思や勧誘の意味でも用いることがある。
(例)どうなっても知らんほん!(どうなっても知らないぞ!) 明日は晴れるほん。(明日はきっと晴れるよ) ほな行ってこほん。(じゃあ行ってくるよ)
原因・理由の接続助詞「さかい」「で」「し」
共通語での「ので」「から」に当たり、「さかい」の後ろには「に」をつけることがある。もとは滋賀県に限らず近畿地方で広く用いてきた表現だが、共通語「から」に押され京阪神では廃れており、滋賀県でも若年層では「から」が優勢になりつつある。湖北・湖西などでは「さけ」となることもある。「で」は湖北・湖東地域を中心に、「し」は湖西・湖南地域を中心に用いる簡潔な表現。
(例)もう年やさかい(に)/やで/やし、無理やわ。(もう年だから、無理だよ)
否定の助動詞「ん」「へん/ひん」「やせん/せん」「なんだ/へなんだ」「んかった/へんかった」
近畿方言では「ぬ」が撥音化した「ん」や「へん/ひん」を否定文に使用する(例:あかん、せえへん、しいひん)。この「へん/ひん」は、「はせぬ」の変形である「やせん/せん」がさらに変化して成立したものである。近江弁でも同様に「ん」「へん/ひん」を用いるが、年配者の間では今でも「やせん/せん」を用い、また「や(あ)る」の否定形に「やあれん」を用いることもある。否定の過去形には、共通語「なかった」が変化した新方言「んかった/へんかった」と、やや廃れつつある旧来の「なんだ/へなんだ」という一般的な近畿方言と変わらないものを用いる。
強調の副助詞「くらい」
湖東・湖北地域で用いる表現で、「くらい」の前につく動詞などを強調する。
(例)するくらい!(するさ/よ!)
命令・禁止の副助詞「さ」
湖東・湖北地域で用いる表現で、近畿方言で一般的な「な」「や」と併用される。
(例)はよしいさ(早くしなよ。一般的な近畿方言では「はよしいな」「はよしいや」)
終助詞「よ」
京阪神ではあまり用いないが、滋賀県では男女問わず多用する。後述「で」とついて「じょ」となることもある。
(例)ほやでよー(だからさぁ) …やけどよー(…だけどさぁ)
音便
他の近畿方言と同様に近江弁でもウ音便が盛んである。また湖東地域では「し」がイ音便化することがあり、その際イ音便後のタ行音がサ行音に変化することがある。
(ウ音便の例)暑くて→あつうて よく笑った→ようわろた
(イ音便の例)傘をさした→傘をさいた/さいさ 腰を抜かしてしまって→腰を抜かいでしもて/抜かいせしもて
s音のh音への転訛
これも近畿方言全般で多く見られることだが(例:すみません→すんまへん)、近江弁は京都・大阪以上にh音への転訛が盛んであり、京都・大阪の出身者からは田舎くさい印象を持たれることがある。
(例)はかい/はけ(上記の「さかい」「さけ」) ほーけー(そうかぁ) ほーよー(そうだよ) ほして/ほて(そして) ほしたら/ほたら(そしたら) ほな(それなら/それでは) ほれで/ほんで(それで) ほやほや(そうだそうだ) ほの(その) ほこ(そこ)
あおぢ
【名】あおたん。内出血。
あこかい
よく知られた近畿方言「あかん」をやんわり強めた派生表現。「あっかい」と促音化することもある。「あこかいや」「あこかいな」などとも。なお「あるかい(=あるわけなかろう)」の促音形「あっかい」という同音異義語もあるので注意。 (例)ほんなことしたらあっかいや。(そんなことしたら駄目じゃないか)
あっちべら
【名】あちら。:水口及びその近隣の地域で主に使われている。「向こうべら」と言う場合もある。なお、「こちら」は「こっちべら」である。
あんない
【形】「味がない」の転訛で、「美味しくない」という意味。
いかい
【形】大きい。古語の「いかし」に由来。 (例)しばらく見ん間(ま)にいこぉなってぇ。(しばらく見ないうちに大きくなって)
いぬ
【動】帰る。古語由来で、漢字では「去ぬ」「往ぬ」と表記する。かつては全県で使われてきたが、共通語の「帰る」におされて使用が減ってきている。
いの
帰ろ。
いんでこほん
「帰って行こう」の意味で、別れるときに使うことがある。
うい
【形】「憂鬱だ」という意味で、古語の「憂し」が由来。アクセントは低・高。「(相手に対して)申し訳ない」というような意味でも使われることがある。 (例)あー、ういなぁ。(あー、憂鬱だなぁ) ほんなことしてもろて、ういこっちゃ。(そんなことをしてもらって悪いことだ)
うたて
【形】鬱陶しい。古語「うたてし」の転訛。
うみ
【名】「海」という意味のほかに、「琵琶湖」という意味でも使われることがある。
えらい
【形】「偉い」のほかに、「とても」「しんどい」「とんでもない」という意味でも使われる。 (例)えらい仕事させられたさかいえらかったわ。(とんでもない仕事をさせられたから疲れたよ)
おおさらしい
【形】大袈裟だ。仰々しい。
おが
【名】カメムシ。
お…やす、…やす
【助動】お…なさい。…ください。 (例)おきばりやす(頑張ってください) お帰りやす(お帰りなさい) ごめんやす(ごめんください) あがっとくれやす(おあがりください) おいでやす(おいでください)
おっさん
【名】お坊さん。「お」にアクセント。フラットに発音すると、共通語の「おっさん」と同じ意味になる。
おまはん
「おまえさん」の転訛である「おまえはん」が縮まったもので、さらに縮めて「おまん」ということもある。「あんた」や「おまえ」よりも丁寧な印象を与えるが、若年層では使われなくなってきている。
かなん
「かなわぬ」の転訛で、「嫌だ」「やりきれない」という意味。京都や大阪でも通じる。
かばた
【名】水路に設けられた作業場のことで、漢字で書くと「川端」。「川端」は湖西地方で使われ、湖東地方では「かわと」(川戸)と呼ばれる。NHK特集で高島市新旭町針江地区の川端が紹介され、注目を集めた。
参考リンク:高島市新旭町針江地区ホームページ内「川端のご案内」
きずつない
【形】古語の「ずちなし」(=どうしようもない。困り果てたことだ)に「気」を合わせたもので、「どうしようもない状態に置かれて、(恥ずかしさなどで)その状態でいるのが申し訳なく感じられ、耐えるのがつらくて気が滅入っている様子」というような意味。 (例)人前でヘマをしてもて、気ずつなかったわ。(人前でヘマをしてしまって、どうしようもなく恥ずかしかったよ)
ごえんさん
【名】ご住職さん。「御院様」の変形。
こぼつ
【動】壊す。古語由来で、漢字では「毀つ」と表記する。
ごもく
【名】ゴミ。
じしん
【名】地震。「じ」にアクセントがくる。
…したらわ?
「…したらどう?」という意味の女性表現。
じん
【名】「人」をあえて音読みで読んだもので、対象の人物に対する相当な侮蔑が込められている。 (例)あのじん、ホンマうっさいわ。(あいつ、ホントうっせぇよ。)
…しとみない
「…するのは気が引ける」「~するのはなんとなく嫌だ」という意味。「…しとむない」とも。 (例)行きとみないなあ。(なんとなく行くの嫌だなあ)
知らんてる
知らないでいる。 (例)知らんてる間(ま)に大きいなって。(知らないうちに大きくなって)
すいばり
【名】ヤスリのかかっていない材木の角などにある木のトゲ。
せんどする
「くたびれる」の意で、「えらい」「しんどい」よりも強いニュアンス。「まるで仕事を千度(千回)するように感じるほど疲れる」ということから。湖北地方などで使われる派生語に「おせんどさん」(=お疲れさん)がある。 (例)あー、せんどした。(あー、くたびれた)
たいや
【名】法要の事。頭に「お」をつけて「おたいや」と使う場合もある。
だんない
【形】差し支えない。大丈夫だ。同義語に「構いはせぬ」の変形である「かまへん」がある。これは京都と同じ表現であり、大阪では「かめへん」となる。
ちゅんちゅん
お湯などが沸いている様子を表す擬態語。
ちょかちょか
あちこちをせわしなくうろちょろしている様子を表す擬態語。「する」をつけると「あちこち動き回っていて落ち着きがない」「あちこち動き回っていたずらをする」という意味になる。名詞化すると「おちょか」または「ちょか」。「ちょかる」(調子に乗る)や、それを名詞化した「ちょかり」(調子乗り)という派生表現もある。 (例)おちょかせんとき!(うろちょろしないの!/いたずらしないの!) ちょかってんなや!(調子乗ってるなよ!)
つうりんぼ
【名】干し柿。
どうで
どうして。なぜ。湖東地方で使われる。 (例)どうでそうなるん。(なんでそうなるの)
とこ
【名】家。家庭。 (例)うち(ん)とこは。(私の家では)
とさいが
…とだな。強調語。 (例)ほうするとさいが。(そうするとだな) こう暑いとさいが、やる気出えへん。(こう暑いとだ、やる気が出ない)
どんつき
【名】突き当たり。
なまずけない
【形】怠けている。不精だ。だらしがない。 (例)部屋ちっとも片付けんと!なまずけないやっちゃなあ!(部屋をちっとも片付けないで!だらしないやつだなあ!)
…ね
…んち。「…のいえ」が縮まったもの。 (例)うちね遊びに来ぃな。(私んちに遊びに来なよ) 田中さんねは立派な家やなぁ。(田中さんちは立派な家だなぁ)
はしかい
【形】古語の「はしかし」が転訛したもので、(細かいトゲなどが当たって)ちくちくと痛いという意味。派生して、風邪などでのどの奥がひりひりして気持ち悪いという意味もある。麻疹とは関係ない。
びちがく
【動】指先でつねる。
ぶんど
【名】湖北地方の年配者によく使われる、えんどう等の豆のこと。
ほっこりする
【動】疲れる。手を焼いた。疲れがとれてほっとする。
地域によってまったく正反対の意味になる。湖北地方などでは「おせんどさん」と合わせて「ほっこりおせんどさん」(=おつかれさん)となることもある。
…まい
【助動】…しよう。湖北地方などで使われる。 (例)いのまい。(帰ろう)
むっかい
【形】ムズい。「むつかしい」が略されてできた滋賀の若者言葉。
めいぼ
【名】目のイボ、つまり「麦粒種」のこと。東京の「ものもらい」や大阪の「めばちこ」という言い回しに比べて直接的でわかりやすい表現である。
めめんかす
【形】ほんの少しである様子。
ももける
【形】セーター等に毛玉が出来たことを表す。
もりこす
【動】湯水が容器の容量を超えて溢れて出てしまうこと。「漏れる」と「超える」が合わさったものか。 (例)うわ、お風呂のお湯もりこしたーるで!(うわ、お風呂のお湯が溢れ出してるよ!)
もんる
【動】帰る。寄る。「戻る」の転訛か。「もんる」単独ではあまり使われず、「もんてくる」(「もんる」+「くる」=帰ってくる)という表現で多く使われる。なお、彦根市のおいでやす商店街には「もんてくる」をモチーフにした「モンテ」(=寄っておいで)という名の施設がある。
もんろまい
「帰ろう」の意味で、別れるときに使うことがある。「いんでこほん」との明確な使い分けはない。
ようあんたさん
「どういたしまして」に近いニュアンスの表現。主に「おおきに」「おきばりやす」と声をかけられた時の返し言葉として使われる。
よぞくろしい、よぞい
嫌だ。不快だ。湖北で使われる。(「おぞ」ましく「狂おしい」か。)
よばれる
【動】(食事などを)頂く。「御馳走になる」以外にも広く用いる。 (例)こんなんしかあらへんけど、なんなっとよばれて。(こんなのしかないけど、なんなりと食べて)
抜粋してきたけど、こっそり読んでくださいよ。
Posted by ぷーとりある at
12:28
│Comments(4)
2008年10月04日
お願い!
わたくし北陸の超田舎よりこちらにやってきました、たかだか滋賀県民13年目になるものでございます。
ひらたくいうたら、まだまだビギナーよ。滋賀ビギナー。
こんなわたしに道を聞かないでストレンジャーよ。絶対教えられない。そもそも対象となる場所が全然わからない。
意地悪じゃなくて、物理的に無理なのさ。
しかし道歩いてると、必ず道を聞かれるのはどうしてなんだよ。
よっぽどなじんでるのか?口を開けば、限りなくあやしい近江弁が飛び出すちゅうのに。
そーそ、近江弁。近江弁ね。
教えてプリーズ。近江弁て奥が深すぎ。13年たってもわかんない言葉が多すぎるよ。
英語はくもんで教えてくれるけど、近江弁はどこに行ったら教えてくれるのさ。
義母ちゃんの言葉につまづき、義姉の言葉に戸惑い、近所の奥様の井戸端会議で迷走する私に誰か近江弁をレクチャーしてください。
いままで聞いた中でナイス!と思った近江弁。
「ほてから」 それから?
「しりから」 かたっぱしから?
「ほやけん」 そうだよ?
「ほうよ」 そうだよ?
「そうやほん」 そうだよ?
ほら、副詞だけですでにスクランブル。わかんないてば。
そういえば、北陸には各県のタウン情報誌が作成した方言辞典があるんだぜ。ここには、ないの?
近江弁でも作ったらいいのに。ビギナー必携の書になること間違いなし。
ひらたくいうたら、まだまだビギナーよ。滋賀ビギナー。
こんなわたしに道を聞かないでストレンジャーよ。絶対教えられない。そもそも対象となる場所が全然わからない。
意地悪じゃなくて、物理的に無理なのさ。
しかし道歩いてると、必ず道を聞かれるのはどうしてなんだよ。
よっぽどなじんでるのか?口を開けば、限りなくあやしい近江弁が飛び出すちゅうのに。
そーそ、近江弁。近江弁ね。
教えてプリーズ。近江弁て奥が深すぎ。13年たってもわかんない言葉が多すぎるよ。
英語はくもんで教えてくれるけど、近江弁はどこに行ったら教えてくれるのさ。
義母ちゃんの言葉につまづき、義姉の言葉に戸惑い、近所の奥様の井戸端会議で迷走する私に誰か近江弁をレクチャーしてください。
いままで聞いた中でナイス!と思った近江弁。
「ほてから」 それから?
「しりから」 かたっぱしから?
「ほやけん」 そうだよ?
「ほうよ」 そうだよ?
「そうやほん」 そうだよ?
ほら、副詞だけですでにスクランブル。わかんないてば。
そういえば、北陸には各県のタウン情報誌が作成した方言辞典があるんだぜ。ここには、ないの?
近江弁でも作ったらいいのに。ビギナー必携の書になること間違いなし。